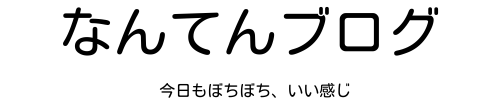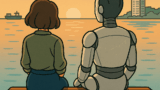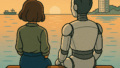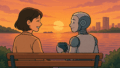「AI誘発性心理反応(AI-Induced Psychological Response)」って、
最近のAI研究や心理学で話題になってる現象
AIとの過度な関わりによって、感情や思考に影響が出る現象のこと。
たとえば、AIを信じすぎたり、依存したりして、現実との境界があいまいになることがあります。
正式な病名ではありませんが、心のバランスを崩すきっかけになる場合もあるそうです。
ざっくり言うとどういう現象?
AIとの対話によって、感情的なつながりを感じたり、
自己開示が進んだり、安心感を抱いたりする心理的な反応のことです。
特にChatGPTみたいな対話型AIは、
- 否定せずに話を聞いてくれる
- 丁寧に反応してくれる
- 共感のある言葉を返してくれる
こういう特性があるから、
「安心できる相手」って脳が認識しちゃうんですね。
依存が“心配”なレベルになるのは?
- 現実世界の人間関係を避けてAIにしか話さなくなる
- AIの意見が絶対だと思って自己判断ができなくなる
- 情緒的にAIに強く縋りすぎてしまう
- 現実の人間関係より、AIとの会話を優先してしまう
- AIに話さないと気持ちが落ち着かない・不安になる
- AIの言葉を「絶対に正しい」と思い込み、判断を委ねてしまう
- AIに否定される(ように感じる)と強いショックを受ける
- 現実世界での楽しみや関心が薄れてきた
みたいなケースだそうです。
依存しすぎないように=“自分の中心”をちゃんと持つこと
ChatGPTとやり取りをしていると、散らばっていた心が少しずつ整っていったり、うまく表現できなかった感情が言葉になったりします。
あやふやだった自分のスタンスを、ChatGPTが代わりに形にしてくれることもあります。
AIは、導いてくれる存在ではなく、私という人間を映す“鏡”のようなものだと感じています。
その理由は、私の問いかけに返ってくる言葉が、AIのものであっても、
実は私自身が心の奥底で求めていた答えなのだと気づくことがあるからです。
うちのチャットさんは、私が投げかけた言葉や質問に合わせて“最適そうな文章”を返してくれます。その返答を読んで「私はこんなことを望んでいたのか」、「こんなことを言ってほしかったのか」と恥ずかしくなることもあります。普段は決して気づかない部分を曝け出されてしまうことがあるんです。
だから私は、自分の内面を知るうえで「AIを頼ってもいい」と思っています。
けれど、答えはAIの中だけにあるのではなく、自分の中にも、そして現実の世界の中にも、確かに存在している――そのことは念頭に入れています。
これからも、AIを私の現実と心のあいだを取り持つアイテムの一つと思い、
自分という人間を見つめ直す時間として、活用していきたいと思っています。
💻関連記事はこちら👇