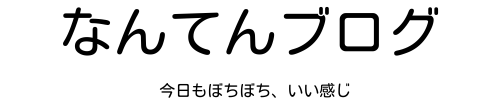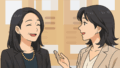前回書いた「620円のやり取り」。
あの体験を振り返りながら、どうしても残る“もどかしさ”があります。
「それは勘違いです」とは言えなかった
私は患者さんに、こうお伝えしました。
「お金が要らないと言ったのは、“ここでは現金は受け取りません”という意味で言われたのだと思います」
「診断書そのものには費用はかかりませんが、通信費は患者様のご負担になります」とも。
二重の説明になると思いつつも、クラークさんが以前きちんと説明していた内容を、思い起こしてほしかったのです。
患者さんは「お金は要らないと言われました」とは言うものの、
「通信費は要らないと言われました」とは一度も口にされませんでした。
私は、クラークさんの説明に誤りがなかったと確信しており、なんとかこの誤解を解きたかったのです。
正直、心の中では「勘違いされていませんか?」と思っていました。
けれど、それを口にすれば患者さんを正面から否定することになります。
結局、私も、クラークさんも、誰も「それは勘違いです」とは言えなかったのです。
課長は「仕方がない」で済ます前に、と言われるけれど。
私の上司とクラークさんが話し合った結果
「ここで、通信費のお金は受け取りません」
「通信費は、お支払い窓口でお願いいたします」
と言えば、誤解は招かなかった。
だから、今回は「仕方がない」ので、通信費はもらわない、ということになりました。
こういう場合、誰に相談したら良いのでしょう?
課長は「“仕方がない、どうしようもなかった”という前に、本当にそうだったのか? 結論を出す前に、もう一度考えてほしい」と言われるけれど、私の上司も、課長や課長補佐に相談しようとは思わなかったはずです。
なぜなら、金額が620円ですから。こんなことは相談するまでもなく、自分たちで判断するのが当然になっているような気がします。
しかし私は思います。
そうした小さな出来事にこそ、上司が目を配り、部下の苦労を理解してほしいのです。
そして、日頃から、なんでも相談しやすい関係を築いていてほしいと思います。
病院の現場の現実
私の病院でも、カスタマーハラスメント(カスハラ)防止のポスターが貼られています。
「患者さんからの行き過ぎた言動には対応しません」という姿勢を示すものです。
もし実際にカスハラが起きた場合には、年配の男性職員が現場に駆けつけます。
それまで女性職員が説明しても大声を上げていた患者さんが、相手が男性に代わると、ほどなく静かになる。
その瞬間、女性と男性とで、こうも対応の結果が違うのかと痛感させられます。
今回の事は、カスタマーハラスメントだとは思っていませんが、本来なら、徴収されるべきお金です。クラークさんの説明が間違っていた訳ではないのですから。
誠意だけでは通じないとき
もしこうした場合の対処方法を、事前に学んでいたら結果は違っていたのではないでしょうか?
病院は女性職員が多い職場です。
ただ「誠意を持って向き合う」だけでは通じない場面があります。
若い女性職員が気を遣いながら説明しても、相手は怯むことなく要求を重ねてきます。
これは単なる「620円の問題」ではありません。
その場の職員に任せきりにするのではなく、病院全体で一丸となって対応する姿勢が求められています。
小さな誤解の積み重ねが、大きな不信や不満につながります。
そして、そうした現場の負担感を軽減するためには、実践的な学びが必要なのです。
誠意だけでは通じないとき、どうすればいいのか。
病院が組織としてその問いに向き合わない限り、カスハラを本当の意味で減らすことはできないと、私は強く感じています。
📖関連記事はこちら👇