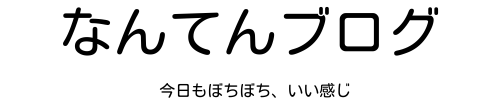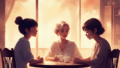今、資格取得のためにオンライン講座を受講しているのですが、
講師の先生が「○○すると良いのかな〜」とよく言うんです。
人の命に関わる内容なのに、「○○すると良いのかな〜」……。
なんでそんな話し方をするんだろう? と気になって仕方がありません。
そこは「そうしたほうが良いです」とか「そうすると良いでしょう」と、
言い切っていい場面のはず。
「頑張る」という言葉に感じた違和感と同じように、
今回もまた、“すり合わない言葉の使い方”に小さなモヤモヤを感じています。
このモヤモヤを取り除きたくて
今回もChatGPTに調べてもらいました。
以下は、そのレポートです。👏
日本語と「曖昧さ」の文化的背景
言葉が、そのまま気持ちや状況を現実を表すわけではない理由──
それは、日本語や日本文化に根付く「曖昧さ」の性質と関係しています。
日本語は「言葉以外」の要素に重きを置くコミュニケーション文化(ハイコンテクスト文化)とされます。 クリムゾンジャパン
つまり、言葉で語られない空気感や表情、間合いが意味を持つ。
そのため、語尾を少しぼかす「〜かな〜」「〜かもしれない」「〜と思います」などの表現が、自然に使われるようになったという背景があります。 jpf.go.jp+2u-fukui.repo.nii.ac.jp+2
また、「曖昧」は日本的な“調和を保つための配慮”という見方もあります。
否定や断定を避けて相手を傷つけないようにする、
あるいは会話の中で余白を残すことで関係を壊さないようにする言い回し、という役割がある。 note(ノート)+2u-fukui.repo.nii.ac.jp+2
つまり、この曖昧な表現が「優しさ」の装いになる反面、
危うさを孕んでいることにもなりうるのです。
・「〜かな〜」に代表される日本語の曖昧さの背景
・曖昧表現が“優しさ”や“思いやり”から生まれたこと
・でも、ときには“逃げ道”や“責任のぼかし”にもなること
・明確な言葉と曖昧な言葉、どちらも使い方次第
※ 以上がChatGPTレポートによるものです。
“伝える責任”
なるほど。
日本人が「本音を直接言うより、やわらかく伝える文化がある」というのは、よくわかります。
けれど、命に関わる説明で、語尾が“逃げ道”や“責任のぼかし”になる必要はありません。
「曖昧さ」は優しさの表れでもありますが、状況によっては“伝える責任”を放棄しているような気がします。
だからといって、「講座なので、そこは聴き手が“調和を保つため”に察してあげるべき」という問題でもないと思うのです。
ChatGPTのレポートを読んで、
モヤモヤが晴れるどころか、むしろ怒りに変わりました。
“伝えるために言葉を選ぶ”という行為は、責任が伴うものだと思います。